Webアクセシビリティが義務化に!

ウェブアクセシビリティは、ホームページがあらゆるユーザーにとってアクセスしやすい状態を指します。高齢者や、視覚障害や聴覚障害などの障害者でも、不自由なくホームページを利用できることが理想です。
2024年4月1日より、障害者差別解消法の改正内容が適用され、民間事業者の「合理的配慮」が義務づけられることになりました。
このことに対応するため3回にわたって解説していきます。
アクセシビリティとは
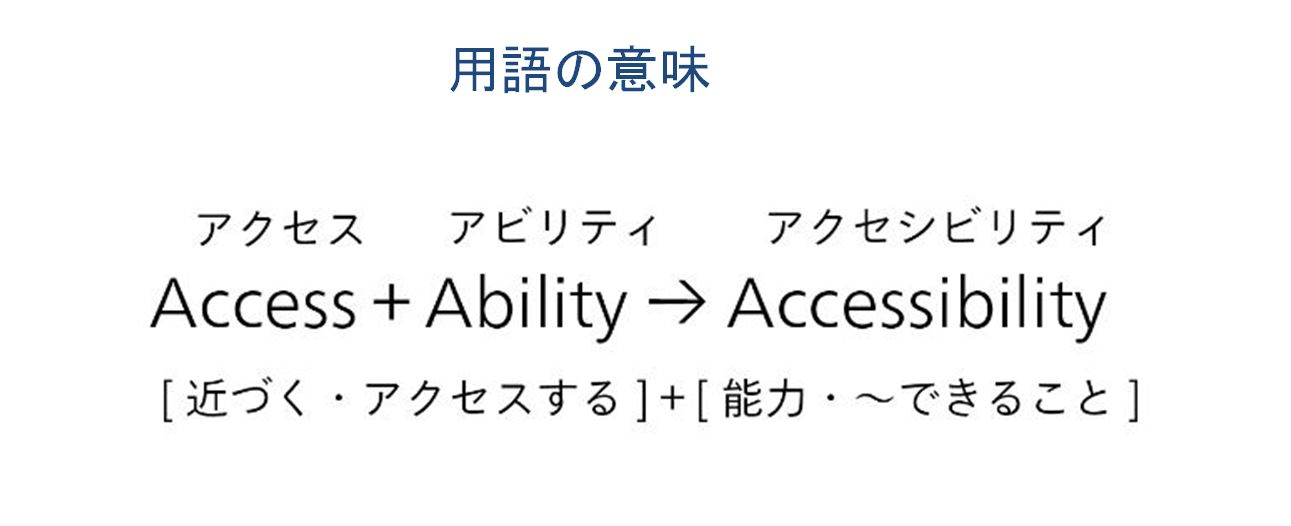
「アクセシビリティ」という言葉は、Access(近づく、アクセスするの意味)とAbility(能力、できることの意味)からできています。
「近づくことができる」「アクセスできる」という意味から派生して、「(製品やサービスを)利用できること、又はその到達度」という意味でも使われます。
ウェブアクセシビリティとは

ウェブサイトで利用者の障害などの有無やその度合い、年齢や利用環境にかかわらず、あらゆる人々が提供されている情報やサービスを利用できることが基本的な狙いです。
ウェブアクセシビリティの低いWebサイト例
障害者特有の問題に関するもの
- 画像に適切な代替テキストがないために、スクリーンリーダーでは理解できない
- キーボードで操作できない
- 音声を聞けないので、動画に字幕(キャプション)が無いと分からない
一般の人に共通するもの。使いにくさについて
- 文字が小さくて読みずらい。色のせいで見にくい
- 文字がテキストリンクなのか分かりにくい
- ボタンがリンクするのか、何を意味するのか分かりにくい
障害の内容

厚生労働省の調査では令和3年度末の時点で身体障害者手帳の所有者が491万人となっています。また障害が無くとも、高齢者や状況によって似たような状況になる場合があります。
なぜ今,ウェブアクセシビリティなのか
さまざまなデバイスの利用

現代社会では、ウェブサイトは重要な情報源で、社会生活を営む上でなくてはならないインフラの一つになっています。
近年、老若男女問わず多くのかたがパソコンやスマートフォンだけでなく、タブレットやゲーム機など様々なデバイスでウェブサイトにアクセスしています。
またネットショップで商品を購入する高齢者が、特にコロナ禍を境に増加しており、もはや日常的な光景となっています。
民間事業者の合理的配慮が義務化
2021年に、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が改正されました。
これにより、国や地方公共団体などに義務付けられている障害のある人への合理的配慮の提供が民間の事業者も法的義務化されることになり、2024年4月1日に施行され,遅くとも、6月4日までに対応する必要があります。
合理的配慮とは社会生活の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としている場合には、負担が重すぎない範囲で対応すること。例えば、日常生活であれば「駅員が車いすの乗客の手助けをする」「窓口で筆談、手話などを用いて意思疎通する」といったことです。
ウェブサイトの場合ではJIS X 8341-3:2016に対応したウェブサイトを作り、ウェブアクセシビリティを確保することがこれに当たります。
ガイドライン・規格
JISX8341-3:2016
JISX8341-3:2016は日本産業規格で「やさしい第三部:ウェブコンテンツ」の部分であり、2016年3年22日に制定されました。
これを遵守しない場合の罰則規定については、今のところ日本では設けられていません。しかし、その場合にはウェブサイトを掲載している会社への世間の評価が下がる恐れがあります。
WCAG2.0
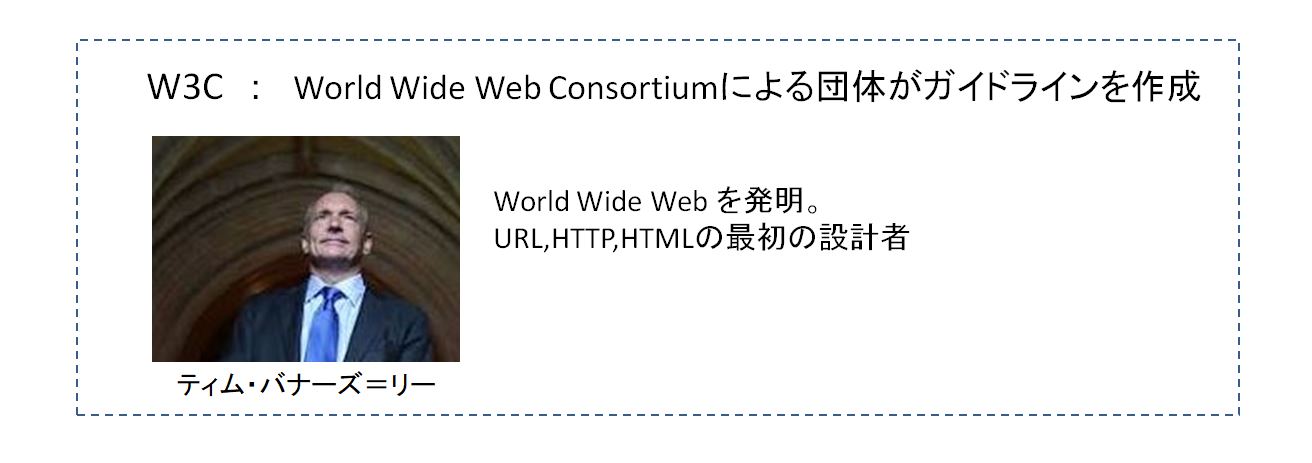
WCAGとはWeb Contnt Accessibility Guidelinesの略で、W3C(World Wide Web Consortium)による団体がガイドを作成しています。
W3Cの代表者はティム・バナーズ=リー氏でWorld Wide Web を発明したURL,HTTP,HTMLの最初の設計者です。
現在,WCAG2.0となっており、内容は国内基準のJISX8341-3と同じです。すなわち世界標準の規格となっています。
「知覚可能」「操作可能」「理解可能」「堅牢(robust)」の4原則とウェブアクセシビリティを向上させる12のガイドラインで構成されています。
WCAG2.0ガイドライン
1:知覚可能
- 1.1 非テキストコンテンツに対して代替テキストを提供し、大きな活字、点字、音声、記号またはより簡単な言語など、人々が必要とする他の形式に変更できる
- 1.2 タイムベース手段を提供する
- 1.3 情報や構造を失わずに、さまざまな方法(よりシンプルなレイアウト等)で表示する
- 1.4 前景と背景を分離するなど、ユーザーがコンテンツを見やすく聞きやすくする
2:操作可能
- 2.1 すべての機能をキーボードから利用可能とする
- 2.2 ユーザーにコンテンツを読んで使用する時間を提供する
- 2.3 発作が起こる可能性のあるコンテンツをデザインしない
- 2.4 ユーザーが移動し、コンテンツを見つけ、どこにいるか判断できる方法を提供する
3:理解可能
- 3.1 テキストコンテンツを読みやすく、理解できるものにする
- 3.3 ユーザーが間違いを回避し、修正できるようにする
4:堅牢
- 4.1 支援技術を含む、現在および将来のユーザーエージェントとの互換性を最大限に高める
他のウェブアクセシビリティの投稿はこちら
ブログの更新はFacebookページでお知らせしています。
ぜひ「いいね」をお願いします!


